共働き夫婦+妊娠中。お金の悩みに向き合った話
結婚して一緒に暮らし始めると、「お金の管理ってどうすればいいの?」という悩みは、誰しも一度は直面するのではないでしょうか。
特に筆者のように共働きで、かつ妊娠中や子育て中となると、今まで以上に生活費や将来の支出が気になり始めます。
私たち夫婦も、妊娠をきっかけに「そろそろちゃんと家計を管理しよう」と話し合うようになりました。
「どちらがいくら払う?」「貯金はどうする?」「お小遣いは?」……決めることはたくさんあります。
最初は手探りでしたが、最終的には「収入に応じて分担し、家計全体をマネーフォワードで「見える化」する」という方法にたどり着きました。
この記事では、そんな私たちのリアルな家計管理のやり方をご紹介しつつ、他の家庭でも役立つであろう管理スタイルの選び方や、失敗しないためのコツをお伝えしていきます。
我が家の家計管理スタイルは「収入割合で負担+見える化」

我が家では、夫婦それぞれの収入に応じて支出を分担して支払いながら、家計全体を「見える化」することで、納得感のあるお金の管理を目指しています。
どちらかが一方的に管理するのではなく、「一緒に把握する」「一緒に動かす」スタイルです。
マネーフォワードで家計を「見える化」
使っているのは、家計簿アプリ「マネーフォワードME」。
銀行口座やクレジットカード、電子マネー、ポイントまで一度登録してしまえばその後は自動連携できるので、アプリを開けば現在の資産状況や支出の内容が一目でわかります。
初回以外、手入力の手間がほぼないので、どちらかに負担が偏ることもなく、家計を「共有」できている実感があります。
「今月ちょっと使いすぎたかな?」という時も、お互いがデータを見ながら冷静に話し合えるのが大きなメリットです。
収入に応じて支払い割合を設定!Excelでルールを明確に
マネーフォワードではいくら使ったかが見えるだけなので、我が家では他にも各自の収入をベースに「何割ずつ生活費を負担するか」を決めています。
たとえば、夫が月30万円、妻が20万円の収入であれば、60:40の割合で家賃や光熱費などを分担。
この支払い割合は、Excelで表にして月々の負担額を明確に管理しています。
半年に1回は割合を見直し、収入の変化に応じて柔軟に調整しているのもポイントです。
お小遣いも「収入の◯%」ルールで不公平感を解消
上記は光熱費や日用品費用ですが、お小遣いについても「それぞれの収入の10%」などのルールを決めることで、不満が出にくい仕組みにしています。
収入を増やせばお小遣いも増える仕組みなので一律「月◯円」と決めるより、負担感が平等になりやすく、家計を一緒に支えている感覚も持ちやすくなりました。
家計管理方法は家庭によって違う!4つのスタイル比較

家計管理の方法に「正解」はありません。
夫婦の性格や価値観、働き方や収入のバランスによって、合う方法は変わってきます。
ここでは、代表的な家計管理の4つのスタイルと、それぞれのメリット・デメリットを簡潔に紹介します。
私たち自身も最初はこの中で迷いながら、自分たちに合う形を模索してきました。
① 全額どちらかが管理(お小遣い制)
いわゆる「妻が家計を一括で管理して、夫はお小遣い制」などのスタイルです。
- 向いている家庭
-
- 片方が家計管理に強く、もう一方が任せたいタイプ
- 専業主婦(主夫)家庭や、どちらかが育休中など収入が一方的な場合
- メリット
-
- 支出を一元管理できるので、全体像がつかみやすい
- 無駄遣いを抑えやすい
- デメリット
-
- お小遣いの金額で揉めやすい
- 管理していない側がお金に無関心&浪費癖になるリスク
② 一定額を渡して、残りは自由に管理
「夫が生活費だけ渡し、残りはそれぞれ自由に使う」といった形。
- 向いている家庭
-
- 給与の差が大きく、片方が主に家計を支える場合
- 金銭感覚が合いにくい夫婦
- メリット
-
- 生活費が決まっているので、無駄遣いを抑えられる
- 自由なお金が確保できるためストレスが少ない
- デメリット
-
- 生活費が足りないときの話し合いが難しい
- 収支の全体像がわかりにくく、貯金がしづらい
③ 収入比で出し合う(我が家はこれ)
共働き家庭に多い方法で、夫婦それぞれの収入に応じて生活費を出し合うスタイル。
- 向いている家庭
-
- 収入に差はあるけど、どちらも収入がある家庭
- 不公平感をできるだけ減らしたい夫婦
- メリット
-
- 「同じ額を出す」よりも納得しやすい
- 残った分は自由に使えるため、ストレスが少ない
- デメリット
-
- Excelに月々の収入を入力するなど、若干管理の手間が増えてしまう可能性がある
- 将来的に大きな支出がある場合に備えた計画は2人で話し合う必要がある
④ 費用項目ごとに分担する
「家賃は夫、食費は妻」など、支出の項目で分担する方法です。
- 向いている家庭
-
- 支出の種類が明確に分けやすい場合
- 個々での金銭管理を重視したい場合
- メリット
-
- 管理範囲が絞れるため、気楽に担当できる
- 担当項目に対する節約意識が高まりやすい
- デメリット
-
- 子どもにかかる費用など、担当が重くなりやすい項目の不公平感
- 全体でどれだけお金が出ているかが見えにくくなりやすい
わが家の工夫とルール(リアルなTips集)

「収入に応じた分担+見える化」という家計管理を続けるうえで、我が家ではいくつかのルールや仕組みを決めています。
お金の話はつい後回しになりがちですが、先にルール化しておくことで、ケンカも減り、お互いにストレスなく過ごせるようになりました。
ここでは、実際に取り入れている工夫をご紹介します。
お小遣いとして割り振った分の使い方には口を挟まない
お互いにお小遣いとして設定した金額については、「自由に使ってOK」というスタンスを貫いています。
たとえその使い道がゲームや趣味への課金、一人外食でも、「お小遣いの範囲内なら本人の自由」とお互いにルール化していることで、無駄遣いに対するストレスやモヤモヤがぐっと減りました。
逆に、口を挟んでしまうと「せっかく自由に使えるはずなのに…」と不満が溜まる原因に。
どちらも自分のために使えるお金があるからこそ、節約や家計のやりくりも前向きに取り組めるようになったと感じています。
家計簿アプリは夫婦で共有
マネーフォワードは、アカウント共有機能を活用しています。
「お金の流れが見える」だけでなく、「お互いの無駄遣いも見えてしまう」点が逆にいいプレッシャーに。
買い物のあと「今月ちょっと使いすぎかも」と気づいたり、片方が頑張って節約していることに感謝できたりと、自然に会話が増えました。
月1回「家計ミーティング」+おやつタイム
毎月1回、支出や貯金の進捗を一緒に見直す“家計ミーティング”を行っています。
といっても、かしこまった場ではなく、おやつや飲み物を用意して「今月どうだった?」と気軽に話すスタイル。
お金のことを真面目に話すと、つい空気がピリつきがちなので、「美味しいものを食べながら」が我が家のルールです。
子どもに関する費用は「育児用口座」を用意
妊娠を機に、児童手当や出産一時金などでいただける助成金や給付金をSBI銀行の目的別口座に「育児用口座」として新たに用意。
ベビー用品・予防接種・保育園関連の支出をこの口座から出すことで、普段の家計と切り分け、見通しを立てやすくしています。
また、将来的に使うことを見越して、毎月数千円でも自動積立を設定し、ムリなく備えるようにしています。
住信SBIネット銀行の使いやすさは別の記事にてご紹介していますので、気になる方は読んでみてください。
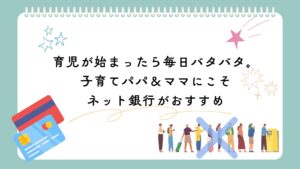
まとめ:お金の話ができる関係は、育てていくもの
夫婦のお金の管理には、正解もゴールもありません。
ライフステージや働き方が変われば、最適な方法も少しずつ変わっていくからです。
大切なのは、「お金のことを一緒に考える姿勢」と、「続けられる仕組みづくり」。
我が家もまだ試行錯誤中ですが、マネーフォワードで家計を見える化し、収入に応じた負担ルールを作ることで、お金の話も前向きにできるようになってきました。
子どもが生まれ、支出が増えるこれからこそ、夫婦で協力しながら家計を支えることが大切だと実感しています。
もし今、パートナーとのお金の管理に悩んでいる方がいたら――
まずは「自分たちに合う方法はどれだろう?」と考えてみてください。
そして、完璧を目指すよりも、お互いに納得できる「ちょうどいい形」を探すことから始めてみてくださいね。
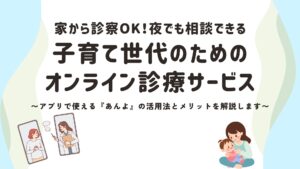
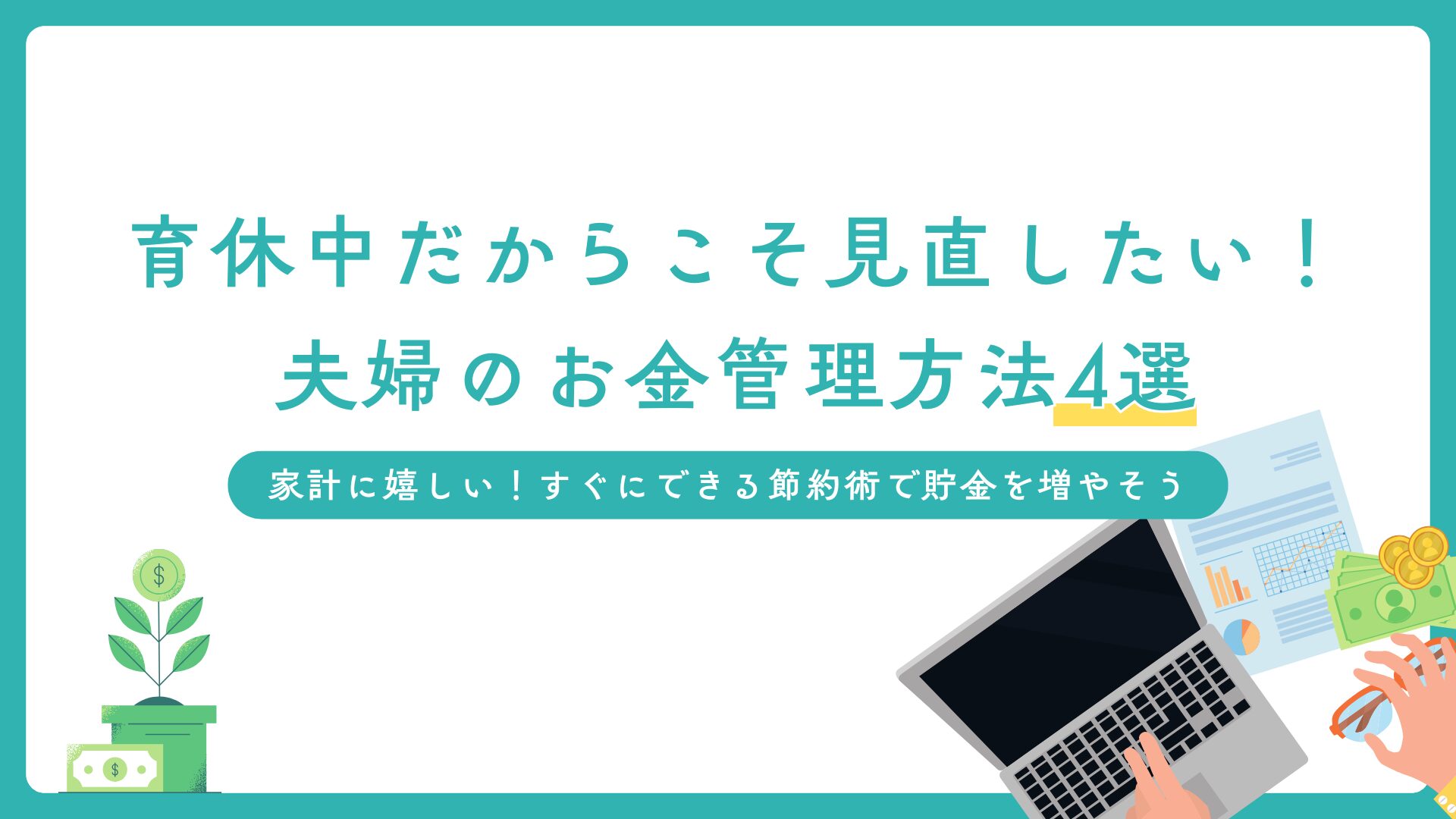

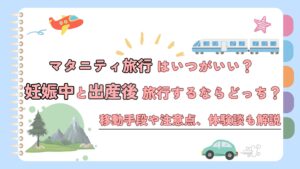
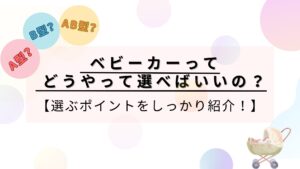
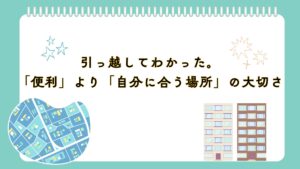
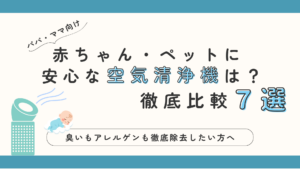
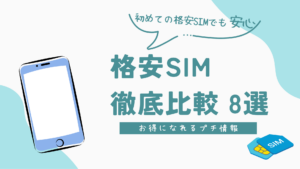
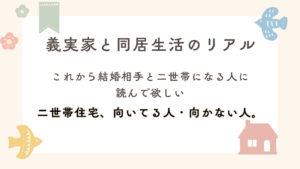
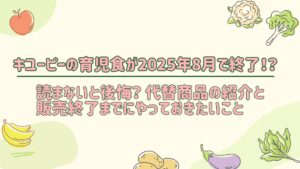
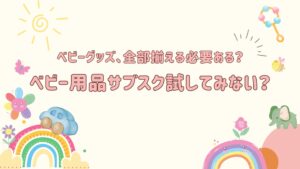
コメント