この記事でわかること
二世帯住宅に憧れていたけれど、「実際に住んでみたらどうなの?」「相手の両親とうまくやっていけるの?」と不安な方も多いのではないでしょうか。
本記事では、筆者が実際に経験した「二世帯住宅でのパートナーの両親との同居生活」をもとに、以下のような内容をお伝えします。
- なぜ二世帯同居を始めることになったのか、その背景
- 一緒に暮らし始めて感じた「ありがたさ」と「後悔」
- 実体験から見えてきた、2世帯住宅でうまくやるためのコツ
- 同居生活が向いている人、向いていない人の特徴
2世帯住宅を検討している方や、現在同居に悩んでいる方のヒントになれば幸いです。
そもそも二世帯住宅とは?基本の形と同居スタイル
「二世帯住宅」とは、親世帯と子世帯の2つの家族が一つの住宅に住むスタイルのことを指します。
近年では共働き世帯や高齢化の進行もあり、選択肢のひとつとして注目され続けています。
一言で二世帯住宅と言っても大きく3タイプに分類されます。
1_ 完全分離型(増築も含む)
完全分離型の二世帯住宅は、同じ敷地内に親世帯と子世帯の生活空間を完全に分けて設けた住まいのスタイルです。
玄関・キッチン・浴室・トイレ・リビングなど、生活に必要な設備がすべて2世帯分用意されています。
建物は一つで内部が完全に分離されているケースもあれば、敷地内に別棟として建てるケースもあります。
外観から見ると「2つの家が合体している」、「離れが建っている」ような状態です。
- 【特徴】
-
- プライバシーがしっかり守られる
- ライフスタイルや生活リズムの違いが気になりにくい
- 共有スペースがないため、トラブルの原因が少ない
- 【こんな家庭におすすめ】
-
- お互いの生活スタイルを尊重したい家庭
- 共働きや夜勤などで生活時間が異なる世帯
- 同居には不安があるけど、近くにいて助け合いたいと考える家庭
- 【注意点】
-
- 同じ敷地のため、時には同居人の視線を感じる時も…
- 建築費用や維持費は高め
- 家の面積や土地の広さがある程度必要
完全分離型は「同じ敷地内での別居」に近いため、「程よい距離感であまり干渉はされたくない」「自分たちのペースで子育てをしたい」など関係を保ちたい家庭には理想的なスタイルだと言えるでしょう。
2_一部共有型
一部共有型の二世帯住宅は、親世帯と子世帯がキッチンや浴室、玄関などの一部を共有しながら、それぞれのプライベート空間を確保するスタイルです。
生活スペースを一部分けつつも、「完全に別」ではないため、日常的な接点や助け合いがしやすい特徴があります。
- 【特徴】
-
- 水回りなどの設備を共有するため、建築コストを抑えられる
- 生活空間が近く、自然とコミュニケーションが増える
- 子育てや介護などでサポートを得やすい
- 【こんな家庭におすすめ】
-
- 育児や家事のサポートを親世帯にお願いしたい家庭
- 高齢の親を日常的に見守れる距離感が欲しい人
- 「ほどよい距離感」での同居を望んでいる人
- 【注意点】
-
- 共有部分の使い方やタイミングでトラブルになることも
- 音や生活リズムの違いが気になる場合がある
- プライバシーの線引きが曖昧になりやすい
一部共有型は、「経済的な効率」と「家族のつながり」のバランスを取りたい家庭に向いています。
ただし、どこまでを共有し、どこを分けるのかは事前にしっかり話し合っておくことが、円満な同居生活のカギになります。
3_完全同居型
完全同居型の二世帯住宅は、玄関・キッチン・お風呂・トイレなど、すべてを親世帯と子世帯で共有するスタイルです。
いわば「昔ながらの大家族」のような形で、生活空間をすべて一緒にするため、日常的な関わりが非常に密接になります。
- 【特徴】
-
- 建築コストが最も安く済む
- 光熱費や生活費をまとめやすい
- 家族全体で家事や育児、介護など出来るので連携しやすい
- 【こんな家庭におすすめ】
-
- 家族間の距離が近くてもストレスを感じにくい家庭
- 育児・介護などで積極的な協力体制を希望する家庭
- 親子間での役割分担が自然にできる関係性の家庭
- 【注意点】
-
- プライバシーの確保が難しい
- 生活リズムや家事のやり方にすれ違いが生まれやすい
- 「誰が何をするか」など、役割の明確化が必要
完全同居型は、家族間の信頼関係が強く、助け合いや協力を前提にした暮らしを望む人に向いています。
ただし、距離が近いからこそ、より配慮しなければいけなくなったりストレスと感じる部分も多くなるため、事前に生活の中でのルールやすり合わせを行うことが大切です。
二世帯同居のきっかけは人それぞれ
同居を始める理由には、以下のようなさまざま背景があると思います。
- 両親からの子育て支援や家事サポートを期待して
- 親の介護や高齢化対策として
- 経済的な事情(家賃・住宅費の節約)
- 親からの強い希望や相続の都合で
筆者自身も、経済的な事情と親側の意向が重なって同居に至りました。
筆者が同居を始めたきっかけ|「ありがたさ」しかなかった同居前の話
ここからは「なぜ妻の実家に同居することになったのか」について、少し長めにお話しします。
興味のある方だけ、読み進めていただければ嬉しいです。
飛ばしていただいてもOKです。
同居のきっかけは「お金」と「余裕のなさ」
私たち夫婦が二世帯同居を選んだ一番の理由は、金銭的な問題でした。
結婚前、妻と二人で賃貸暮らしを始めた頃、家賃も光熱費も「2人で働けばなんとかなる」と思っていました。
実際、私も妻も手取りは13~15万円程度でしたが、収支のバランスは取れているはずだったのです。
ところが、二人暮らし生活が落ち着き始めた頃から、妻が情緒の乱れからだんだんと仕事に行けなくなってしまいました。
当初は「ただの無気力?それとも鬱?」と戸惑いながらも、2人で何度も話し合い、支え合いながら生活を続けていました。(後に、妻はADHDとの診断を受けます。)
当時の私は、お金のことも、妻の体調のことも、すべてにおいて甘く見ていたのだと思います。
想定外の状況に、生活は徐々に困窮。気づけば、銀行ローンに頼り、両家の親からも援助を受けながらどうにか生活を繋ぐ――
そんな地獄のような日々が続いていました。
さらに追い打ちをかけたのが、私が独身時代に無計画に組んでいた車のローン。
将来の収入増を見越したステップアップ型の支払いでしたが、現実は甘くありませんでした。
車購入時の話が気になる方は以下の記事も読んでいただけると嬉しいです。
転職して収入がやや増えても、支払いに追いつかず、毎日が不安と焦りの連続だったことを今でも覚えています。
そんな時でした。
妻の実家から「お金での援助も限界があるから、うちに住まないか」と声をかけてもらったのは――。
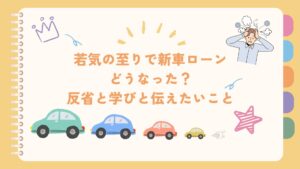
「住まわせてもらえるだけでありがたい」と思っていた
当時の私たちは、金銭面だけでなく、精神的にも限界に近い状態でした。
最初こそ、話し合った上で「増築」で私たちの生活スペースを確保した生活も視野に入れていましたが、ローン返済が多い状況や収入面からローンは通らず…
そう言った経緯があったからこそ、「住まわせてもらえるだけでありがたい」「これで少しは楽になれるかもしれない」――
そうした感情が先に立ち、同居に対して不安や懸念を持つ余裕もありませんでした。
妻の両親も快く受け入れてくれ、義父からは「いずれ跡を継いでくれれば」と声をかけられ、
自然な流れで婿養子としての入籍と同居が決まりました。
あの頃、私たちには「余裕」というものがなかった
振り返ると、当時の私たちにはお金の余裕も、心の余裕もまったくなかったのだと思います。
私は手取り15万円ほどの会社で働き、どれだけ頑張ってもお金は足りない。
そんな不安とプレッシャーに押しつぶされそうな中で、
「せめて安心して暮らせる場所を確保したい」――
その思いだけで決断した同居でした。
本来なら、将来の暮らし方や義実家との関係性を冷静に見極めてから判断すべきだったのかもしれません。
けれど当時の私たちは、「今をどう乗り切るか」だけで精一杯でした。
今思えば、勢いと切羽詰まった状況が私たちの背中を押していたように思います。
生活が始まって見えてきた「後悔」と現実
「住まわせてもらえるだけでありがたい」
――そう思って始まった二世帯住宅での生活。
けれど、いざ一緒に暮らし始めると、感謝の気持ちだけでは乗り越えられない「現実」が次々と見えてきました。
義母の「目」と「干渉」に疲れてしまった
義母はアパート時代から娘(妻)の様子を頻繁に気にして車があるかなどの確認をされていましたが、同居が始まってからはその干渉が一層強くなりました。
- 外出して車がなかっただけで「どこ行ってたのかな?」と話題にしていることを祖母から聞く
- 忙しい時間を避けて義母は料理しない時間帯で料理していても「まだかかるの?」と急かされる
- ケーキや惣菜など、外で買ってきたものを部屋で食べていると「私のご飯が食べれないの?」「非常識だ」と非難される
感謝の気持ちがあっても、四六時中見られているような生活は、やはり心が休まるものではありませんでした。
「家族のはずが…」義母の言動がもたらす分断とストレス
義母の言葉や態度は、次第に私たち夫婦の関係にも影響を及ぼすようになりました。
- 妻との仲の良さに対して嫉妬のような態度を見せる
- 気に食わないことがあると、陰で妻に「婿養子なのに…」と告げ口される
- 夫婦で飼っている猫が鳴いた際に「叩いた」と祖母に話していたことを聞かされる…(怪我は無く、叩いた強さは不明ですが…)
日常の中で、傷つく出来事や不信感が少しずつ積み重なり、「家族」としての温かさよりも、「気に触ることのないように気を張る生活」になっていったのです。
精神的にも金銭的にも追い詰められていく暮らし
生活費を抑えるための同居だったはずなのに、実際にはそう上手くはいきませんでした。
- 当初の家賃額から義母が金額をどんどん上げようとしてきた
- 義母自身は生活費を支払っておらず、義父側にもお金を渡していなかった
- 新聞配達などのバイトで朝2時に出勤し、帰宅後4時半頃に風呂へ入った際にお風呂の濡れ具合を見て「また朝風呂?」と嫌味を言われる(音が響くような間取りではないです。)
次第に私(夫)は適応障害を発症。義母の言動について義父に相談しても「家族なんだから、仲良くやっていくしかない」と言われるばかりで、根本的な解決には至りませんでした。
同居していた頃に関係を円滑にするために心がけていたこと
同居中は、とにかく日々の人間関係に気を遣う毎日でした。
特に気をつけていたのは「言葉のトーン」と「態度」です。何気ないひと言でも、相手の受け取り方ひとつで空気が悪くなることがあったため、義母との会話ではできるだけ言葉を選ぶようにし、語気を強めないように心がけていました。
「ありがとうございます」や「すみません」といった基本的な挨拶も、意識的に口に出すことで、こちらの誠意が少しでも伝わればという思いでした。
生活のリズムについても、極力義家族の流れを乱さないように配慮しました。
たとえばお風呂や洗濯は義両親が使わない時間帯を選び、キッチンの使用も重ならないよう工夫。当たり前ですが、深夜や早朝に行動する際は、足音や物音に気をつけるなど、静かに過ごすよう気を配っていました。
また、住まわせてもらっている立場だからこそ、感謝の気持ちは常に意識していました。
たとえすべてが報われるわけではなかったとしても、できるだけのことはしてきた。
そう思えることで、自分たちの気持ちを保ち、なんとか関係を円滑に保とうとしていた記憶があります。
2世帯住宅に向いている人・向かない人
二世帯住宅は、経済的な助け合いや介護・育児のサポートといった点で魅力的な選択肢ですが、誰にでも向いているとは限りません。
実際に同居してみてはじめて分かる「相性の問題」も多く、事前に自分たちが向いているかどうかを見極めることがとても大切です。
まず、二世帯住宅に向いている人の特徴としては、以下のような傾向があります。
二世帯に向いている人
- 家族間の距離が近くてもストレスを感じにくい
- 生活リズムや価値観の違いに柔軟に対応できる
- あらかじめルールを決めておけるタイプ
- 育児や介護のサポートを必要としている
- 家族のつながりや助け合いをポジティブに捉えられる
こうした人たちは、多少の干渉やすれ違いがあっても「お互い様」と思える柔軟さがあり、適度な距離感を保ちつつうまく生活していける傾向があります。
二世帯に向いていない人
一方で、二世帯住宅に向かない人はこんなタイプかもしれません。
- 自分の生活ペースや空間を強く大事にしたい
- 親や義家族との距離感をしっかり取りたい
- 人に干渉されるのが苦手、またはプライバシーを重視したい
- 感情をため込みやすく、不満をうまく伝えられない
- 義家族との関係性がもともとよくない、または距離がある
こういった方にとっては、日常的な気遣いや価値観の違いがストレスになりやすく、「ちょっとしたこと」が積み重なって後悔のきっかけになることも少なくありません。
実際に私自身、当初は「助けてもらってありがとうございます」と思っていましたが、思った以上に精神的な距離が縮まらず、かえって自分たち夫婦の関係にも影響してしまう場面がありました。
大切なのは、経済面や一時の感情だけで決めず、「自分たちの生活スタイルや性格に合っているか」まできちんと考えることです。勢いで決断してしまうと、後々大きな溝になることもあります。
【まとめ】同居は幸せ?それともストレス?私が感じたこと
振り返ってみると、二世帯住宅での同居生活は「ありがとうございます」という気持ちと「ストレス」が表裏一体でした。
当初は、経済的に追い詰められていたこともあり、「住まわせてもらえるだけでありがたい」と感じていました。実際、生活費が抑えられることで一瞬は精神的に楽になった部分も確かにありました。
しかし、その反面で、家族間の距離が近すぎるがゆえに、自由やプライバシーが制限されることが増え、息苦しさや気疲れを覚えることも多々ありました。
些細な言動や視線、言い回しひとつで雰囲気が不穏になったり、夫婦の関係にも思わぬ影響が出ることもありました。
それでも同居を通じて、「自分たちがどんな暮らしを理想としているのか」「家族との距離感をどう保てばいいのか」といった大切な価値観に気づくことができたのは、大きな学びだったと思います。
同居が向いている人もいれば、そうでない人もいます。環境が与えてくれる安心もあれば、乗り越えるべき課題もある――それが二世帯住宅の現実です。
だからこそ、「何となく」「流れで」決めるのではなく、生活の価値観や優先したいことを夫婦でしっかり話し合ったうえで選ぶことが何より大切なのだと、私は身をもって感じました。

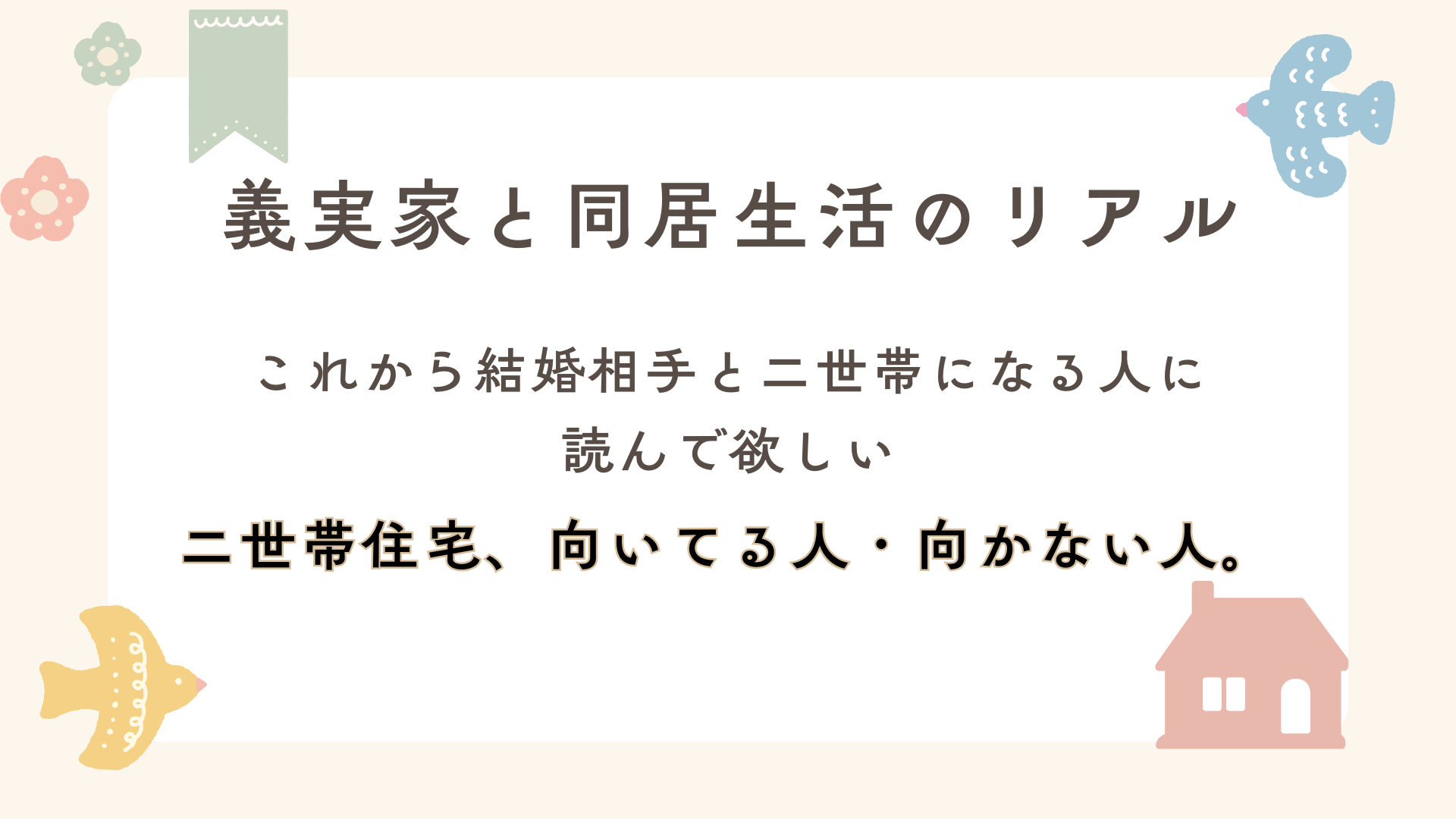

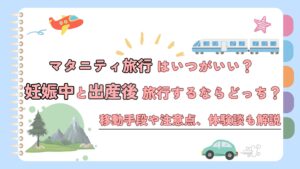
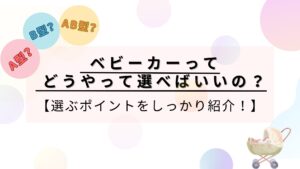
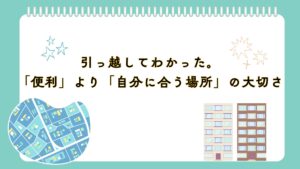
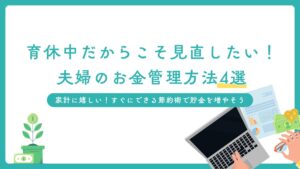
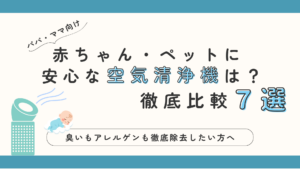
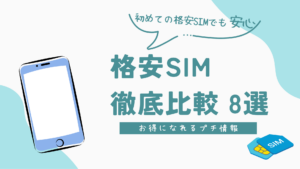
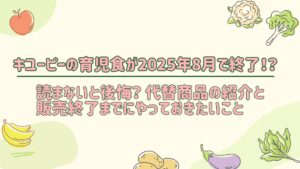
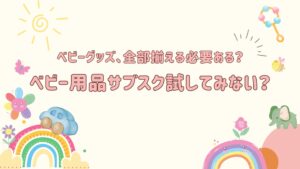
コメント