この記事でわかること

妊娠中や出産後に旅行を考えるとき、
「赤ちゃんがお腹にいるうちに行った方がいいの?」
「出産後の方が安心?」
「飛行機や車での移動は大丈夫?」
と、気になることがたくさんありますよね。
この記事では、以下の内容をわかりやすく解説します。
- 妊娠中の旅行で絶対に持って行った方が良い持ち物
- 妊娠中と出産後、旅行に行くならどっちがおすすめか
- 飛行機・車・新幹線など、交通手段ごとの注意点
- 筆者が妊娠中に旅行を検討したとき、医師から聞いたアドバイス(体験談)
- 赤ちゃんと出産後に旅行する際の注意点やタイミング
妊娠中のマタニティ旅行を検討している方や、赤ちゃんが生まれた後の旅行を考えている方に向けて、安全で安心な旅行の計画づくりに役立つ情報をまとめました。
妊娠中と出産後、旅行に行くならどっちがおすすめ?

妊娠中に旅行に行くメリット&デメリット
出産後に旅行に行くメリット&デメリット
妊娠中に旅行をするなら、パパさんにも積極的に話に参加してもらい、体調や週数をしっかり確認した上で、無理のない計画を立てることが大切です。
次のセクションでは、妊娠中に旅行する際に医師へ確認しておきたいポイントや、旅行計画の立て方の注意点を詳しく解説します。
妊娠中に旅行しても大丈夫?医師に確認しておきたいこと

結論から言うと、妊娠後〜出産後で旅行に行くならば「妊娠中の安定期に、近場へ無理のない計画で行く」のがおすすめです。
出産後は赤ちゃんとの思い出作りもできますが、授乳やおむつ替え、荷物の多さなどで移動が大変になります。特に生後間もないうちは、感染症のリスクや体調管理の難しさもあり、長距離旅行はハードルが高めです。
一方で、妊娠中であれば荷物も少なく、夫婦2人でゆっくり過ごせる最後のチャンス。安定期で体調が落ち着いている時期を選び、電車や新幹線で行ける近場の旅行なら、安心して楽しめます。
妊娠中でも、体調や妊娠週数によっては旅行が可能な場合があります。
ただし、自己判断は絶対にNG!必ず主治医に相談してから計画を立てることが大切です。
特に妊娠初期は体調が変わりやすく、移動や環境の変化が母体や赤ちゃんに負担をかける場合があります。
旅行前に医師に確認しておきたいこと
- 旅行に行っても良い体調・週数かどうか
※安定期(妊娠16週〜27週頃)が比較的安心と言われますが、体調は個人差があります。 - 移動手段についての注意点(飛行機や長距離移動など)
- 持病や妊娠経過に応じて注意すべきことはあるか
- 旅行先で急な体調変化があった場合の対応について
- 36週以降は旅行は控える
※いつお産が始まってもおかしくない時期のため、遠出は避けましょう。
ただし、安定期でも体調が優れないときは無理をせず、旅行を見送る判断も必要です。
旅行中に気をつけたい4つのポイント
- 必ず主治医に相談してから旅行を決める
- 余裕を持ったスケジュールを組む(体調に合わせて柔軟に変更できるように)
- 体調に合った移動手段を選ぶ(同じ姿勢を長時間続けない、こまめに水分を取る)
- 自分の妊娠経過を把握し、緊急時に説明できるようにする
体調が少しでも不安なときは、迷わず旅行を中止する勇気を持つことも大切です。
次のセクションでは、電車・新幹線・車・飛行機など、交通手段ごとの注意点を解説します。
マタニティ旅行でおすすめの交通手段と注意点&必需品

妊娠中の旅行では、移動手段によって体への負担が大きく変わります。
特に長時間同じ姿勢でいると血栓ができやすくなるため、こまめな休憩や水分補給が大切です。
ここでは、電車・新幹線・車・飛行機それぞれの注意点と、旅行に持って行きたい必需品をまとめます。
電車・新幹線の場合
おすすめ度:★★★★★(特に妊娠中は安心な移動手段)
- 移動中に立ち上がれるので、血流が滞りにくい
- トイレがあるため安心
- 事前に指定席を予約しておくと移動がスムーズ
- 混雑時間帯を避け、余裕のあるスケジュールにする
車の場合
おすすめ度:★★★☆☆(運転手の慣れや距離に注意が必要)
- 周囲を気にせず移動できるので気楽
- 荷物を積み込みやすく、休憩場所も自由に選べる
- ただし、長距離運転は運転手の負担も大きくなるため、運転に慣れている人が同行することが必須
- 1〜2時間ごとに休憩をとり、車外で少し歩いて体を動かすのがおすすめ
飛行機の場合
おすすめ度:★☆☆☆☆(どうしても必要な場合を除き、避けた方が安心)
- 気圧の変化や長時間の座席での拘束が体に負担になる場合がある
- 妊娠中は血栓ができやすく、エコノミー症候群のリスクも上がる
- 航空会社によっては、妊娠後期の搭乗に医師の診断書が必要な場合もある
筆者夫婦が沖縄に行こうと医師に相談した際も、「どうしてもという理由がない限り、妊娠中の飛行機移動はおすすめしない」と言われ断念しました。
旅行に持って行くべき必需品
- 母子手帳
- 健康保険証
- 診察券
- 羽織りもの(体温調節のため)
- 生理用ナプキン(突然の出血や破水に備えるため)
- 常備薬や主治医に処方された薬
- 緊急連絡先(かかりつけ医・家族など)
どの移動手段を選ぶ場合でも、妊娠中は「体調最優先」で計画することが大切です。
無理な長距離移動や詰め込みすぎたスケジュールは避け、こまめに休憩を取りながら、安全に楽しめる方法を選びましょう。
出産後に旅行する場合のポイントと注意点

赤ちゃんが生まれた後は、家族で旅行を楽しみたいと思う方も多いですよね。
ただし、新生児期や生後間もない赤ちゃんとの旅行は、母子ともに負担が大きく、注意が必要です。
旅行はいつからが安心?
- 生後3カ月以降が目安
➡️ 免疫が少しずつつき、授乳や生活リズムも安定し始める時期。 - 首が座る5〜6カ月頃以降がより安心
➡️ ベビーカーや抱っこ紐での移動もしやすくなる。
出産後の旅行で気をつけること
- 母体の回復を最優先に
➡️ 出産後は、体力やホルモンバランスの回復に時間がかかります。無理をせず、産後健診で医師に相談してから計画しましょう。 - 授乳・おむつ替えがしやすい環境を選ぶ
➡️ 授乳室やオムツ替えスペースがある赤ちゃんがOKな施設・ホテルを事前にチェック。 - 感染症のリスクに注意
➡️ 赤ちゃんは抵抗力が弱いため、人混みや流行期の旅行は避けた方が安心です。
出産後旅行の移動手段のポイント
- 電車・新幹線は指定席を予約して、ベビーカーや荷物の置き場所を確保する
➡️ 余裕があれば、1席多めに取っておくと、広々と使えて周囲の目を気にせず過ごせるので安心です。 - 車移動は赤ちゃんの様子を見ながら、休憩を多めに取る
➡️ 運転手の眠気防止や赤ちゃんの授乳やおむつ替え、機嫌に合わせて、1〜2時間ごとに休憩するのがおすすめです。 - 飛行機は泣き声や耳の痛みなどの対応も必要になるため、まずは短時間の移動から慣らすのがおすすめ。
➡️ パパママ交流会で聞いた話では、離着陸時に授乳やあやしで対応できると、フライト中は赤ちゃんは意外とおとなしいことが多いそうです。
ただし、対応がうまくいかないと気圧の変化で泣き続けたり、吐き戻しが起きることもあるため、事前に対策しておくと安心です。
赤ちゃんとの旅行は、授乳・オムツ替え・荷物の多さなど、妊娠中よりも準備や配慮が必要になります。
無理に遠出をするのではなく、まずは日帰りや近場の宿泊から少しずつ慣れていくのが安心です。
私の体験談|妊娠中に旅行を検討したときの医師からのアドバイス

私は妻の妊娠初期の頃に、2人きりの旅行はしばらく出来なくなると思い、沖縄旅行を急遽計画したことがありました。
飛行機に乗ることに少し不安があったため、旅行のプランを練る段階で念の為、主治医へ相談しました。
そのとき医師から言われたのは、
「どうしてもという理由がない限り、妊娠中の飛行機移動はおすすめしない。行く際は自己責任でお願いします。」
という言葉でした。
理由としては、
・長時間座ったままで血栓ができやすくなる
・気圧の変化で体に負担がかかる場合がある
・万が一、旅行先で体調を崩してもすぐに対応できないリスクがある
といった点が挙げられました。
この話を聞いて私と妻は、「今無理して行く必要はない」と判断し、旅行を見送り、近場の電車や車で完結できるところに行くことにしました。
もちろん体調や状況によって判断は変わると思いますが、医師に相談してから決めて本当に良かったと思っています。
この体験からも、現在妊娠中で旅行を検討している方には、行き先や移動手段、母体の状態によってリスクが変わるため、自己判断せず必ず主治医に相談してほしいとお伝えしたいです。
繰り返しになりますが、母体と赤ちゃんのためにも、体調と安全面を最優先に考えてください。
まとめ|出産前に旅行するなら、近場&無理のない計画がおすすめ!
妊娠中と出産後、どちらのタイミングで旅行するか迷う方は多いと思います。
結論としては、もし妊娠中に行くなら妊娠中の安定期に、電車や新幹線で行ける近場へ無理のない計画で出かけるのがおすすめです。
出産後は赤ちゃんとの思い出作りができますが、授乳やおむつ替え、荷物の多さなどで移動の負担が大きくなります。
特に生後間もない時期は感染症のリスクも高く、母体の回復も十分とは言えないため、旅行は慎重に検討する必要があります。
一方、妊娠中であれば身軽に行動でき、夫婦二人でゆっくり過ごせる最後の貴重な時間になります。
ただし、旅行を計画するときは必ず主治医に相談し、体調や週数を考慮した上で、余裕のあるスケジュールを組むことが大切です。
無理をせず、母体と赤ちゃんの安全を第一に考えながら、思い出に残る楽しい時間を過ごしてください。
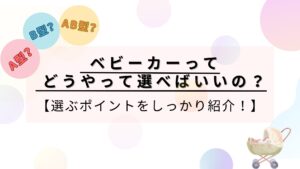
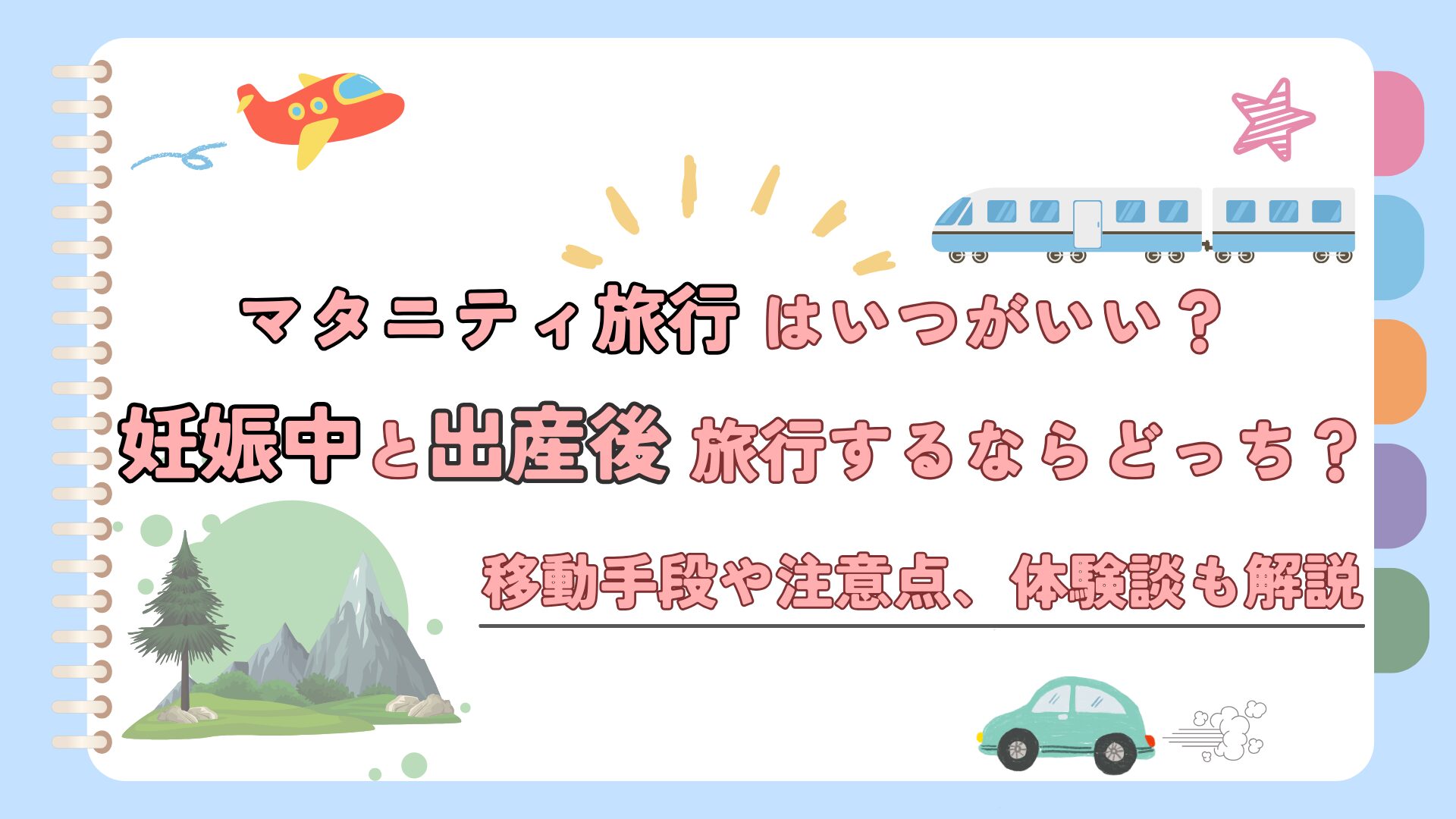

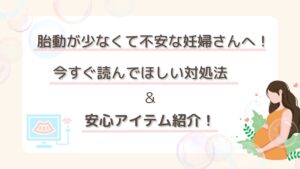
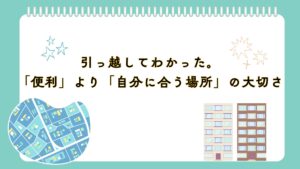
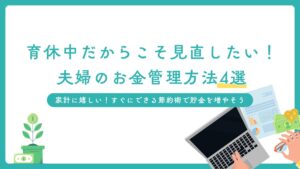
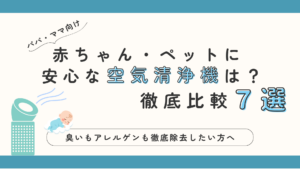
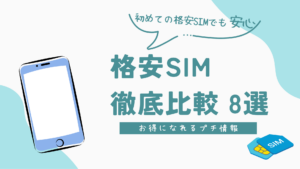
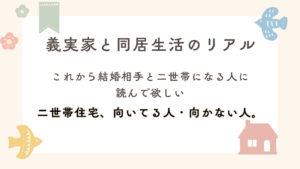
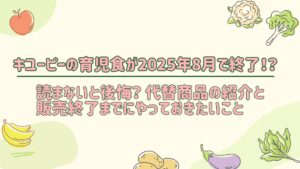
コメント